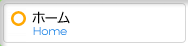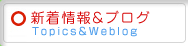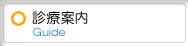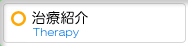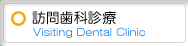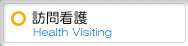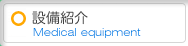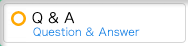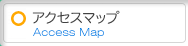新着情報
全日本歯科医師親善ボウリング大会@品川



|
【歯科医師親善ボウリング大会】
品川プリンスホテルBCにおける全日本戦に初めて参加しました。在宅診療をほぼ毎日行っている私ですが、患者さんはご高齢で足腰に不具合を生じている方が多いためか、2年位前から体幹トレーニングも兼ね、約30年ぶりに競技ボウリングを始めました。 本大会今年で51年め、歴史のある集いです。参加資格は歯科医師で総勢184名、上位28名(ラインは平均195点位)が決勝に進みます。種目は、個人戦・2人チーム戦・4人チーム戦(3種目予選9ゲーム)を2日間で競います。試合が進み、体が自然と大学時代のハードさを思い出していました。 戦績は、初日1ゲームめ138点と最悪のスタート、2日め最終9ゲームめでやっと200点越え(243点)しましたが、9ゲーム合計点が1,600点位、まるでダメです (※全日本ではパーフェクト(300点)がハイゲームとなる等、どちらが本業なのか分からない位、毎回すごいドクターが出てきます) 1日めの夜「懇親会」にて、ボウリング界では神様的存在である矢島純一プロ(第1期生)が登壇されました。閉会後私が帰り際、他府県歯科医師会所属の同窓先輩先生に突如声掛けされカメラ係を担い、その勢いに便乗し私も記念に撮ってもらいました。 お祭り騒ぎ的に私は真ん中に押し込まれる等、とてもにぎやかなひと時でした。 世界でも活躍される矢島プロ(2枚目の写真右側)と日々臨床に携われる歯科医師の先生方との交流は、私にとって一生の宝物です。ありがとうございました。皆さん、健康に留意し今後も頑張りましょう。 【追記】本大会、動画投稿(http://www.youtube.com/watch?v=7jW5LMsQFO4)されたものがありました。Y先生「個人総合シニア準優勝」誠におめでとうございます。 (※私は5:10と5:50付近に10秒位映っています) 写真クリックすると拡大できます。 (2016年9月) |
むし歯菌と脳出血との関係



|
【むし歯菌と脳出血との関係】
先日むし歯の原因菌として知られるミュータンス菌の一種が脳内で炎症を引き起こし、脳出血の発症に関与しているというトピックスが、国立循環器病研究センター(国循・大阪市吹田市)等で発表されました。厚生労働省の調査で、成人の9割以上はむし歯があり、ほとんどがむし歯菌を持っているとされています。今回の国循によると、コラーゲンと結合して血小板の止血作用を低下させる「cnm遺伝子」を持つ特殊タイプは約1割占めており、保有株が検出された患者は脳出血の発症可能性が他の患者よりも約4倍あり、核磁気共鳴画像法(MRI)でも確認できる微小な脳出血の跡も多かったとのことです。通常、血管の傷口に菌の「コラーゲン結合タンパク質」が集まり血管の修復を図って止血されますが、この特殊な菌が血管壁に付着し炎症を伴うことにより歯肉からも出血しやすくなり歯周組織が壊されます。高血圧や過剰な長期的ストレス、老化、喫煙等でも血管壁がもろくなり破れやすくなるので「歯みがきでの口腔ケアや歯科治療等で衛生的に保てば脳出血患者の再発予防や発症リスクを低下させることもある」との見解も出ています。みなさまの健康維持のためにも「かかりつけ医療機関」での早期受診をお奨めいたします。 (2016年2月)
(【1枚目の写真】右が「コラーゲン結合タンパク質」を持つむし歯菌を投与し脳出血を発症させたマウスの脳、左は無投与 【2枚目の写真】スプーンに付着した黒い粒がミュータンス菌 【3枚目の写真(※画像クリックで拡大参照ねがいます)】母親(周囲の大人)が口移しで同じスプーンを使用した際などに唾液を通じて感染し,子供のむし歯危険度が2倍以上高いというデータがあります)
|
麻酔学講習会@文京シビックホール



|
【麻酔学講習会】 先日、東京歯科保険医協会主催の学術研究会に出席させていただきました。
笑気吸入鎮静法(20~30%の笑気ガスを酸素とともに吸入)・表面麻酔(針入時の痛みを軽減するため粘膜への麻酔方法・リドカインテープを使うと15秒で鈍覚になるとのこと)・麻酔薬(カートリッジ保管法)・無痛浸潤麻酔(切り口の向き・刺入(点)と抜針)・伝達麻酔等々,日々臨床に直結する内容で講義が進みとても参考になり,翌日からの診療に早速反映させました。
講師の砂田氏は同窓で同時期に在学された先輩先生であり,随所に懐かしい恩師の名前が挙げられ,まるで大学附属病院内で受講しているような厳しさと安堵感がありました。 また講義が始まる10分位前,目の前を歩かれた受講者が在学中私が大変お世話になった口腔外科のN助教授(当時)先生でした。約25年ぶりにお会いでき激励のお言葉までいただき,誠にありがとうございました。 (※恩師と突然お会いすると未だ直立不動となり,また怒られるかと思いました) いつも分かりやすく素晴らしい講義をされた当時の成書(教科書)・ノート等を、開業医となった今でも時おり繙き(ひもとき)ます。 このような機会をご提供いただいた協会スタッフ及び皆さまに感謝申し上げます。 (2015年6月) |
介護予防と口腔ケア@梅丘パークホール



|
【介護予防と口腔ケア】
平成27年4月12日、世田谷区歯科医師会主催「口腔介護講演会」@梅丘パークホールに出ました。本日の講師は、昭和大学歯学部教授(スペシャルニーズ口腔医学講座・口腔リハビリテーション医学部門)の高橋浩二先生です。大学と同じ約1時間半の講義でしたが、簡易的に骨子をお知らせさせていただきます。
食べ物を上手に噛む(咀嚼・そしゃく)為には、舌を使い噛み合わせ場所に送り込み、さらに唇や頬の筋肉を緊張させ咀嚼されたものが噛む場所より外側に落ちないようにしながら、下顎を動かすことが重要です。
噛むことを十分行った後,口やのどを複雑にしかも絶妙なタイミングで動かし,飲込み(嚥下・えんげ)を行います。
75歳以上になると肺炎の死亡率が急増します。誤嚥(ごえん)性肺炎の原因として口内細菌があげられ、口内を清潔にする(口腔ケア)ことがKeyとのこと、「粘り強い痰を口外に出す方法(排痰法)」「歯牙・粘膜・義歯・口内全体のクリーニング法」「頬側にたまった食べ物除去法」「頬の筋肉のトレーニング法」「舌の運動法」「構音(こうおん)訓練」等々のテーマで話され、最後に個々の実習も行われました。
配布された飲み物にパウダーを入れ、約30秒かき混ぜ2~3分でトロミの出来上がり、そして初めての試食となります。感触として無味無臭の寒天状でしたが、トロミの濃さも調整出来てベストな介護食品という心証です。 食べる幸せ・生きる力は健口からでもあり、日々在宅訪問診療に携わる歯科医師として、今後も皆さまの健康寿命に少しでもお力添えしていきたいと思います。
【追記】受講席の真後ろに、私が約30年前歯科大学在籍中、実習担当医として直接ご教示いただけたK先生がいらっしゃいました。K先生は、現在世田谷区歯科医師会の幹部ドクターとしてご活躍されています。 閉会後の慌ただしいさ中、ご厚誼いただき深謝申しあげます。 (2015年4月) |